概要

課題・ソリューション・導入効果
ビジネスの課題
高負荷サービスの安定運用と効率化の両立を目指して
テクノロジーとマーケティング力を用い、新しい価値の創造を目指す CARTA HOLDINGS。同社が手がけるデジタルマーケティング事業、インターネット関連サービス事業の中で、Web サイトやスマホアプリの事業者向けにマネタイズ支援を行っているのが fluct です。同社の主力サービスの 1 つ SSP『fluct』は、最適な広告を自動で配信して広告収益を最大化するプラットフォームで、2010 年のリリース以来、機能強化を続けてきました。SSP『fluct』は月間数千億回以上の広告リクエストに対応する必要があり、低いレイテンシーと高い可用性が求められます。当初はこれをオンプレミスのサーバーで運用していましたが、固定的なリソースでは効率的に対応するのが難しく、特にエンジニアリング面ではハードウェアやネットワーク機器の管理に特化した人材が必要でした。「オンプレミス環境ではすべて私たちで管理する必要があるため、常に人的リソースの課題がありました。できる限りマネージドサービスを活用したいという思いはあったものの、クラウドにともなうコストを懸念して移行に踏み切れない状況にありました」と語るのは、株式会社 fluct 執行役員 CTO の大渡裕太氏。
オンプレミス環境の問題に対応すべく AWS を併用するハイブリッド環境へと移行していましたが、オンプレミスでの運用を続ける限り非効率な運用や大規模な投資、データセンター側の障害リスクへの懸念は残りました。そこで 2020 年、利用していたデータセンターの一部が廃止されることを契機に、fluct を全面的に AWS へと移行する決断を下しました。AWS を選んだ理由について、fluct の移行を担当したプロダクト開発本部 プラットフォーム部 部長の中崎満晶氏は、「すでに AWS を利用していたのでチームにとって馴染みやすく、サポート体制も充実していたので、移行の難しさは特に感じませんでした」と語ります。
経営視点での判断について、当時 fluct の取締役 CTO で、現 CARTA HOLDINGS 執行役員 CTO の鈴木健太氏は、「クラウドへの全面移行は単純なコスト比較だけでなく、人的リソースの効率化も含めて総合的に判断しました。移行にはアプリケーション側の変更も伴いましたが、経営陣との協議で『将来のアジリティを買う』ことに合意が得られ、移行が決まりました」と当時を振り返りました。
ソリューション
リフト&シフトからアーキテクチャ最適化へ
fluct の AWS への全面移行は、AWS の支援プログラムである AWS Migration Acceleration Program(MAP)を活用し、段階的に実施されました。移行は 2020 年 11 月にスタートし、約 1 年かけて既存のシステムを EC2 インスタンスを中心としたクラウド環境に移行。この過程では、アプリケーションなどの既存システムには最小限の変更で対応し、旧データセンターの廃止前に移行を完了することを目指しました。そして、2021 年末にはすべてのデータセンターからクラウドへの移行が完了しました。
クラウド移行完了後は、システムアーキテクチャの最適化フェーズに入りました。「Amazon Aurora などのマネージドサービスの活用や、スポットインスタンスや AWS Graviton プロセッサを積極的に採用することで大幅なコスト最適化を実現しました。最近では、Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)の活用も進めております。また、ログ収集や集計基盤についても、Amazon Kinesis Firehose を活用してデータを Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)に保存することで、より簡便に運用できるマネージド構成へと移行しました。最新のサービスを常にキャッチアップして、アーキテクチャのアップデートを続けているため当初のシステム構成の面影はほとんど残っていません。その時の最新技術を常に適用し続けられるのも AWS を活用しているメリットだと思います」と大渡氏は語ります。こうしたアーキテクチャの見直しは、ビジネス要件やチームの効率性を考慮して、あるいは新技術の登場をきっかけに行われています。中崎氏は「たとえば、コストが上がったときには現状のままでよいのかを検討し、開発に時間がかかっている場合には、より効率的な方法を模索します。私たちの組織にはエンジニア主導の文化が根付いているため、エンジニアがビジネスの初期段階から関与し、ビジネス要件に対してどう最適な形を実現するかを常に考えながらアップデートしています」と、常に最適化を図っている点を強調しました。
導入効果
エンジニアの負担を軽減しながら、データベース移行期間を大幅に短縮
AWS クラウドへ全面移行したことで組織醸成にも大きな変化をもたらしています。まず最も顕著な効果として、インフラ運用の負荷が大きく軽減され、エンジニアの採用と育成のハードルが大きく低下しました。
「クラウド環境移行により、物理的なサーバー管理やネットワーク機器の専門知識を持つエンジニアの確保が不要になりました。オンプレミス時代はデータベースのアップグレードを慎重に手作業で行い、ダウンタイムの影響を考慮しながら数か月かけて進めていましたが、現在は AWS の活用により手順が効率化され、インフラ構築未経験のエンジニアがゼロから取り組んで 1 か月もあれば完了できるようになっています。インフラのコード化(Infrastructure as Code)に注力し、AWS CloudFormation 等を活用して環境の再現性と変更の容易さを高めることで、インフラ構築の経験が少ないエンジニアでも、迅速に環境を整えることができるようになりました」と大渡氏は語ります。
インフラのコード化によって普段アプリケーションを書いているエンジニアであっても環境の構築に手を出しやすくなり、AWS の豊富なサービスにアクセスできるようになったことで、イノベーションのスピードも加速しています。鈴木氏は「クラウドの最大の利点は、気軽にチャレンジでき、失敗してもすぐに元に戻せることです。ネットワーキングや他のサービスとの連携もすべてプログラムで対応でき、クラウド上で完結できるようになりました。エンジニア個人のできることが増えたのは、非常に大きなメリットです」と話しました。
さらに、AWS の最新サービスの活用とコスト最適化は、事業の収益性に直接貢献すると同時に、顧客に還元できる価値の向上にもつながっています。鈴木氏は今後もデータ活用の領域において、さらなる進化を目指していきたいと話します。「デジタルマーケティングではデータの活用が非常に重要な意味を持つため、データの利便性や可用性、安全性など、クオリティを高めた形でインテグレーションしていければと思います。データを効果的に活用するには地道にデータを整理していく必要がありますが、AWS と協力しながらこれらの課題を解決する機会を模索していきたいと考えています」(鈴木氏)
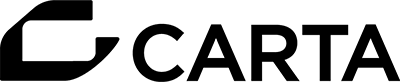
クラウドへの全面移行は単純なコスト比較だけでなく、人的リソースの効率化も含めて総合的に判断しました。AWS を選んだ理由はすでに社内で使用実績があったこと、またエンジニアチームの馴染みやすさと手厚いサポートも決め手となりました
鈴木 健太 氏
株式会社 CARTA HOLDINGS 執行役員 CTO株式会社 CARTA HOLDINGS
取組みの成果
1 か月 - データベースのアップグレード期間
スケーラビリティが向上し、トラフィック増減に柔軟に対応可能
インフラ運用負荷を軽減し、エンジニア採用育成のハードルが低下
コスト最適化により、事業収益性が向上
新技術やサービスへのアクセスが容易になり、イノベーションが加速
本事例のご担当者
鈴木 健太 氏

大渡 裕太 氏

中崎 満晶 氏
